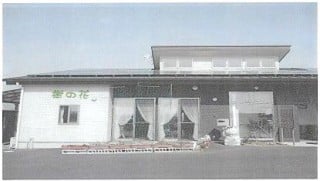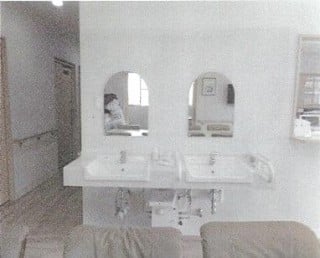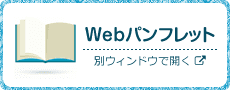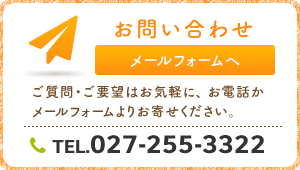はなみずきでは、
こどもたちが社会参加するために
必要な「生きる力」を育てることを
目指した支援をしていきます。
こどもたちが社会参加するために
必要な「生きる力」を育てることを
目指した支援をしていきます。
はなみずきからのお知らせ
2024-03-06
2024-03-06
2022-03-03
2022-03-03
2023-03-09
| もっと見る |
施設紹介
事業内容
| 放課後等デイサービスとは | 児童福祉法に基づく障害児通所支援事業です。学校通学中の障がい児が、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上のための訓練等を継続的に提供することにより、学校教育と相まって障害児の自立を促進するとともに、放課後等の居場所づくりを行います。 |
| 対象児童 | 学校教育法に規定する学校(幼稚園、大学を除く)に就学しており、授業の終了後又は休業日に支援が必要と認められた障がい児 |
施設名 | 放課後等デイサービス 樹の花はなみずき |
所在地 | 〒371-0852 前橋市総社町総社2602-1 ページ一番下にマップあります |
電話番号 | 027-212-0015 |
ファックス番号 | 027-212-0016 |
| 利用定員 | 10名 |
| 実施地域 | 前橋市、高崎市、吉岡町、榛東村 |
開設日 | 月・火・水・木・金・土 但し年末年始(12月29日~1月3日)を除く |
開設時間 | 9:00~18:00 |
サービス提供日 | 月・火・水・木・金・土 但し年末年始(12月29日~1月3日)を除く |
サービス提供時間 | 学校授業日 14:30~17:30 土曜、祝日、学校休業日 10:00~16:30 土曜 祝日だけでもご利用できます。 ※上記以外はご相談ください |
| サービス内容 | 多様なプログラムを準備。
本人の希望や障がい特性に応じたサービスをご提供いたします。
個人・集団活動における遊びや学習を通して、児童の自立を促進するとともに、放課後等の時間を充実して過ごせるように支援します。 |
送迎が可能です | 学校授業日 学校⇔事業所⇔自宅 学校授業日以外 自宅⇔事業所⇔自宅 |
スタッフ | 管理者、児童発達支援管理責任者、中高等学校教論、保育士、児童指導員 |
ご利用料金
ご利用料は、放課後等デイサービス事業の法定利用料に準じています。法定代理受領(9割分)を伴うサービス提供の場合は、下記給付費の1割及び実費費用が1日当たりの実際にお支払いただくご負担額になります。 ※単位数に単価を乗じたものが金額となります。(前橋市の1単位単価は10.18円です。) ・放課後等デイサービス給付費 604単位(学校休業日に行う場合は721単位) 604単位×10.18円=614円のうち原則1割(614円)が1回あたりの負担金額となります。 ※職員の体制及び利用者に該当がある場合に下記の加算がかかります。(かかる場合は事前にお知らせします。)送迎加算(往復の場合)108単位(片道54単位)児童指導員等加配加算、福祉専門職員配置等加算、欠席時対応加算、延長支援加算 等 令和3年度法改正により個別サポート加算(Ⅰ)が創設されました。(該当児童)※ただし、ご負担には世帯所得により月額上限額が決められており、それを超える負担は頂きません。 例)世帯所得が約890万円までの方の月額上限額は4,600円です。仮に1ケ月で20日間利用になった場合でもご負担額は4,600円となり、1日当たり230円のご負担で利用できます。
ご利用者様の負担上限額(受給者証)
世帯所得
| お支払料金
|
非課税世帯
| 0円
|
約890万円まで
| 月額上限 4,600円
|
約890万円以上
| 月額上限 37,200円
|
その他の実費
おやつ代 100円(1日につき)
創作活動にかかる材料費等の実費・屋外活動時の費用等(費用が発生する場合は、事前にご連絡致します)
ご利用案内
持ち物について
(1)連絡ノート(事業所で用意いたします。)
(2)上履き
(3)学習用具(宿題、学習プリントや学習ドリル、鉛筆、消しゴム等)
(4)着替え用のズボンや下着、タオル、ハンカチなど必要に応じて。
(5)歯ブラシ・コップ・歯磨き粉(土曜日、祝日、また長期休暇中のご利用時)
※持ち物にはお名前の記入をお願いします。
ご利用までの流れ
(1)お電話ください。
ご見学の日時を決定致します。
ご見学の日時を決定致します。
(2)ご見学・面談
児童発達管理責任者からはなみずきの内容など詳しくご説明させて頂きます。
重点的に支援していく内容などをお伺い致します。
ご利用される曜日や送迎時間のご希望などを決めてゆきます。
児童発達管理責任者からはなみずきの内容など詳しくご説明させて頂きます。
重点的に支援していく内容などをお伺い致します。
ご利用される曜日や送迎時間のご希望などを決めてゆきます。
<ご持参頂くもの>
受給者証
(3)ご利用契約
活動内容
樹の花はなみずきでは日常の支援の中に ソーシャルスキルトレーニング(SST)を用いてご利用児が社会で生きていくうえで必要な技術を習得するお手伝いをします。
たとえば、
・指示を理解したり、判断したりするのが苦手
・得意なことと不得意なことに大きく偏りがある
・自分の行動をコントロールするのが苦手
・人とのコミュニケーションが苦手
・運動が苦手
・情緒が不安定
などが対象のお子さん達です。
たとえば、
・指示を理解したり、判断したりするのが苦手
・得意なことと不得意なことに大きく偏りがある
・自分の行動をコントロールするのが苦手
・人とのコミュニケーションが苦手
・運動が苦手
・情緒が不安定
などが対象のお子さん達です。
<支援の例>
■ あいさつをする
あいさつは、人とのコミュニケーションには欠かせないものです。ところが子どもの中にはどこでどのようにあいさつをすればよいかが分からなかったり、あいさつの言葉を口に出すのが恥ずかしかったりと、さまざまな理由からあいさつができない子どもがいます。 適切なタイミングで適切なあいさつの言葉を発することができるようになるためには、「大人が積極的にあいさつをする」こと、「あいさつを強要しないように気をつけること」が大切です。「あいさつをすることは気持ちがよいこと」「相手の気持ちが嬉しくなること」ということを子どもが肌で感じられるような環境を作っていきます。
■ 順番を守る
公園の遊具に乗るとき、バスに乗るとき、お店に並ぶときなどに、つい並んでいる人の間に入ってしまったり、「一番」じゃないといやだと駄々をこねてしまったりする子どもがいます。一番であろうとすること自体は決して悪いことではありません。しかし順番を守ることができないと、そこからけんかに発展してしまったり、相手から嫌な印象を持たれてしまったりとトラブルになってしまう可能性があります。 そうならないために大人ができることは、「日頃から自分が順番を守り、その姿を子どもに見せる」、「子どもが順番を守れたときに褒める」、「一番じゃなくても大丈夫だということを伝える」などです。順番を守れなかったからといって叱るのではなく、自然に順番を守れるようになるために日々の生活から習慣を身につけていくことが重要です。
■ 相手の気持ちを察する
子どもの中には、相手の気持ちを理解することが苦手な子どもがいます。相手の表情から気持ちを読み取ることが苦手だったり、共感するということが苦手だったりと理由はさまざまですが、時にはそれが人とのかかわりにおいてネガティブに働いてしまうことがあります。 そんな子どもがうまく相手の気持ちを読み取れるようになるために、多くのSSTの方法が考えられています。たとえばゲームを用いたもの、ロールプレイを用いたもの、絵カードを用いたものなどです。「嫌なことをされたとき自分はどう思うか、その嫌なことを実際にされている相手はどんな気持ちか」を考えたり、今相手が考えていることを意識的に想像したりする訓練をすることで、実際の生活でも自然と相手の気持ちを理解できるようにサポートをします。
■ 会話をする
上記に挙げたように、相手の気持ちを理解することが難しい場合などは、相手を傷つける言葉を言ってしまったり、相手にとって興味のない話をひたすら話し続けてしまったりという言動につながってしまうことがあります。相手の気持ちをくみ取り、適切な話題・話す時間・使う言葉を選んで進めていく会話は、多くのステップを含んだソーシャルスキルなのです。 多くの要素を含む会話だからこそ、その訓練は「決められた質問(自分の名前など)に答える練習をする」というものから「シナリオに従って言葉のキャッチボールの練習をする」というもの、「おしゃべりタイムを設けて振り返りを行う」というものなど多岐にわたります。
■ ほめる
社会性を身につけている大人から見ると、社会のルールに従うことのできていない子どもの行動は目につくものとしてとらえられるかもしれません。しかし、子どもにとって叱られたり注意をされたりすることは嬉しいことではありません。それどころか、叱るという行為は社会性を鍛えるのに逆効果の場合もあるのです。 できないことを叱るのではなく、できたことを認めて褒めるということが子どもが楽しみながら自然に社会性を身につけていくのに重要なポイントなのです。 ■ スモールステップを踏んでいく 冒頭でも述べたようにSSTを必要とする子は、生まれてから育っていく中で自ら周りの人を観察して、社会性を身につけていくのが苦手な子どもです。そのため、一般的に当たり前だと思われる会話や行動・思考が自然にできないケースが多く見られます。 同時に、その子がそれまで積み上げてきた「当たり前」も存在します。その当たり前を変えるのには長い時間と、多くの小さなステップを踏まなければなりません。指導する側に立つ人は、長い目で物事をとらえ、ゆっくりと成長を見守っていく姿勢が必要なのかもしれません。